2025年11月1日、富山県高岡市に本社を構える加越能バスが、一般路線バスの初乗り運賃を160円から200円に改定します。
この値上げは、消費税以外では実に28年ぶり。
同時に、1kmあたりの基準賃率も48円10銭から58円60銭に見直されることが、北陸信越運輸局により認可されました。
当記事では、この運賃改定の概要とその背景、加越能バスを取り巻く経営環境、地域交通の展望、そして利用者やネット上での反応などについて深掘りします。
加越能バスの運賃改定の概要
加越能バスが発表した今回の運賃改定は、2025年11月1日から実施されます。
主な変更点は下記のとおりです。
・初乗り運賃:160円 → 200円
・基準賃率(1kmあたり):48円10銭 → 58円60銭
・平均改定率:約22.18%
この改定により、短距離利用者だけでなく、中・長距離区間でも運賃が全体的に上昇します。
運賃制度の大枠そのものが見直されることとなり、日常的に利用する市民にとっては大きな影響があります。
今回の申請・認可は、国の交通行政のもとで正式な手続きを経たものであり、バス会社単独の判断ではありません。
※画像はイメージです。
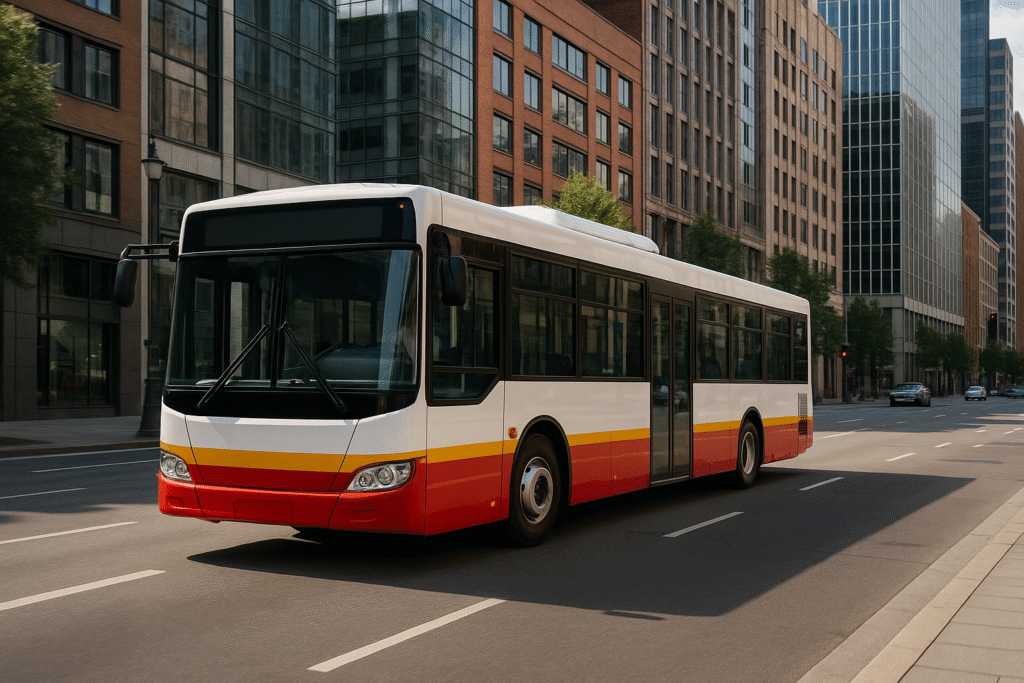
値上げの背景にある3つの理由
1. 利用客の減少による収益悪化
地方都市では少子高齢化や自家用車の普及により、バスの利用者が長期的に減少傾向にあります。
加越能バスも例外ではなく、定期券利用者や通学・通勤客の減少により、収益が安定しづらい状況が続いています。
2. 運転士の人件費高騰と確保の難しさ
運転士の高齢化、人材不足も深刻な問題です。
安全運行を維持するには、待遇改善による雇用確保が不可欠であり、そのための人件費が上昇しています。
また、労働時間の管理や休日確保といった労務負担の増加も、運賃改定の一因です。
3. 車両・設備への投資と修繕費の増加
バス車両は定期的なメンテナンスや買い替えが必要であり、部品や燃料費の高騰も経営を圧迫しています。
さらに、ICカード対応機器の導入や運行管理システムの近代化など、ICT投資も避けられません。
今後の加越能バスと地域交通の展望
利用促進と利便性向上の取り組み
運賃値上げは痛みを伴いますが、その一方でサービス維持・改善への期待も高まります。
加越能バスでは、回数券やシルバーパス、学生割引などを通じて、利用者の負担軽減を図っています。
将来的には、ダイヤの柔軟な見直しや、地域コミュニティバスとの連携なども視野に入れられています。
自治体や市民との協働による交通維持
バス路線は単なる移動手段ではなく、「地域インフラ」としての価値も持ちます。
高齢者の買い物・通院、学生の通学など、生活の足を守るには、行政・住民・事業者の協力が欠かせません。
利用者やネット上での反応と声
利用者の声
・「高くなるのは困るけど、ドライバーさんの賃金を考えたら仕方ないかも」
・「200円ならまだ安い方…だけど、通勤で毎日使うときつい」
・「もっと本数増やしてほしい。値上げだけじゃなく、サービス改善を!」
ネット上での傾向
ネット上では、今回の値上げについて、
・「やむを得ない」
・「理解できる」
とする声がある一方で、
「不便な路線はこのまま減らされるのでは?」
といった将来への不安も見られます。
特に高齢者や学生からは、定期代や家計への影響を懸念する意見が目立ちます。

まとめ
加越能バスの初乗り運賃値上げは、長期的な経営維持と地域交通の持続可能性を見据えた苦渋の決断です。
もちろん、利用者としては「値上げ=負担増」と感じるのが当然です。
しかし一方で、公共交通の担い手を守り、サービスを維持するためには一定の理解も必要です。
これから私たちができるのは、「バスを積極的に利用すること」、そして「声を届けること」。
加越能バスが引き続き地域の“足”であり続けるために、利用者1人1人の行動が求められています。










コメント