2025年9月11日、富山県南砺市の小中学校および義務教育学校で提供された給食を食べた105人の児童・生徒・教職員が食中毒症状を訴える事件が発生しました。
原因は「ヒスタミン中毒」と特定されており、給食で提供された魚「フクラギ(ブリの幼魚)」が原因とみられています。
当記事では、この事件の詳細やヒスタミン中毒のリスク、再発防止のための対策などについて深堀りします。
食中毒の詳細
富山県によると、給食を食べた直後から唇の腫れや発疹といったアレルギー様の症状が出たと報告されました。
医療機関を受診したのは12人、幸いにも入院者は出ていません。
検査の結果、給食で提供された「フクラギの梅みそ焼き」に使用されたフクラギの切り身から、高濃度のヒスタミンが検出されました。
ヒスタミンは、ブリやサバなどの赤身魚が常温で長時間放置されることで生成される物質で、食べるとアレルギーに似た中毒症状を引き起こします。
この中毒は「ヒスタミン中毒」と呼ばれ、潜伏期間が短く、摂取後すぐに症状が出るのが特徴です。


なぜ汚染が起きたのか?
今回の事件で、富山県は調理施設に大きな問題はなかったと発表しています。
つまり、加熱処理などの調理工程自体は正しく行われていたということです。
しかし、ヒスタミンは加熱しても分解されないため、原材料の保存段階ですでに発生していた可能性が高いとされています。
今回の給食には、複数の業者や流通経路が関与しており、具体的な汚染経路は特定できていないのが現状です。
現在、県は関係する施設に対して衛生指導を行いながら、引き続き調査を進めています。
ネット上での反応と声
ネット上では、今回のヒスタミン食中毒事件に対して、多くの声が上がっています。
・「子供にこんなことが起きて心配」
・「フクラギは普段から食べている魚なのに…」
・「給食の安全管理って本当に大丈夫なの?」
SNSでは、学校給食の安全性や流通経路の管理体制に対する不信感が広がっており、保護者を中心に再発防止への強い要望が寄せられています。
一方で、
・「調理現場に問題がなかったことに安心した」
といった声や、
・「流通段階のチェック体制を強化すべき」
といった建設的な意見も見られました。


まとめ
今回の事件は、魚の取り扱いにおける温度管理の重要性を再確認させるものでした。
ヒスタミン中毒は、見た目や匂いで判別できないため、事前の予防が何よりも大切です。
学校や給食施設での対策
・魚類の仕入れ時の温度管理の確認
・原材料の納入元の信頼性チェック
・食材保管庫の定期的な点検
家庭でもできる予防策
・魚は購入後すぐに冷蔵や冷凍保存する
・解凍後はすぐに加熱調理する
・赤身魚の常温放置は避ける
今後も、子供たちが安心して給食を楽しめるよう、行政・教育機関・家庭が一丸となって安全対策を徹底していく必要があります。
当記事は以上となります。

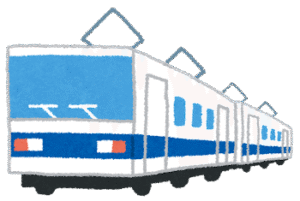



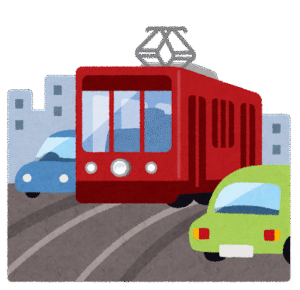

コメント