富山県サッカー協会が2030年代前半の開業を目指す「まちなかスタジアム」構想が注目を集めています。
富山市の中心部に、サッカー専用の多機能複合型スタジアムを建設し、地域の賑わい創出を目指すこのプロジェクト。
その成功のカギとして挙げられているのが、長崎県の「長崎スタジアムシティ」の成功事例です。
当記事では、長崎での実例をもとに、富山での成功に必要なことについて掘り下げます。
成功事例の長崎スタジアムシティとは?
「ピーススタジアム」は2023年9月に長崎市の中心部に誕生した、J2クラブ「V・ファーレン長崎」の本拠地です。
観客席とピッチの距離はわずか5メートルと、日本一臨場感ある観戦が可能な設計。
最大2万人収容の全席屋根付きスタジアムは、雨の日でも快適に観戦でき、平均入場者数は以前の約2倍、新規来場者も1試合あたり1500〜2000人増加するなど、その集客力が注目されています。
※画像はイメージです。

非試合日でも賑わうスタジアムの工夫
「日常的に開放されたスタジアム」が、長崎スタジアムシティの最大の強みです。
試合がない日も朝7時から夜11時まで一般開放され、地元住民が勉強や食事、散歩などに利用できる憩いの場になっています。
子供たちが遊び、高校生が勉強し、大人がリラックスする――。
まさに“日常”がスタジアムに根付いていることが、高い来場者数と地域への愛着につながっているのです。
ジャパネットが作る唯一無二の空間
スタジアムシティは、通販大手ジャパネットグループが総事業費約1000億円を投じて開発した民間主導のプロジェクトです。
ジップラインや温浴施設、ホテル、ショッピングモール、オフィス棟など約80の店舗と複合施設が一体化されており、スタジアムというよりは“まち”そのもの。
観光客やビジネスパーソンも取り込む仕組みで、地域経済への波及効果も期待されています。
成功のカギは地域密着と民間の創意工夫
公共施設では難しいような“尖った”発想こそが、民間主導型スタジアムの魅力です。
例えばホテルの客室からスタジアムが一望できる設計や、スタジアム上空を滑走するジップラインなど、他にはない体験価値が来場者の心をつかんでいます。
また、地元企業のオフィス誘致やBリーグのホームアリーナ併設など、地域と継続的な関係性を築く工夫も見逃せません。
ネット上での反応と声
ネット上では、
・「子供も大人も楽しめる場所」
・「スタジアムのイメージが変わった」
・「長崎に住みたくなる!」
といった声が多く寄せられています。
特に、試合がない日でも利用できる点に対する評価が高く、「スタジアムが日常にある暮らし」への憧れを抱く人も。
富山でも同様の声が上がるような設計が求められています。

まとめ
長崎スタジアムシティの成功から見えてくるのは、スタジアムを「非日常のイベント空間」から「日常の暮らしの一部」へと変える発想の転換です。
富山が目指す“まちなかスタジアム”の実現には、アクセスの良さ、多機能性、そして民間主導による創意工夫が欠かせません。
スタジアムが市民の誇りとなり、街の活力を生み出す新たな拠点になることが期待されています。



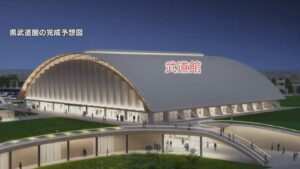






コメント